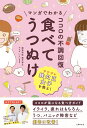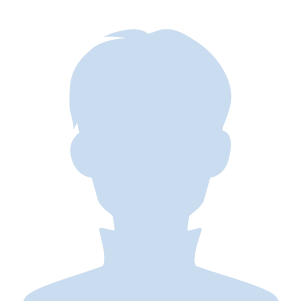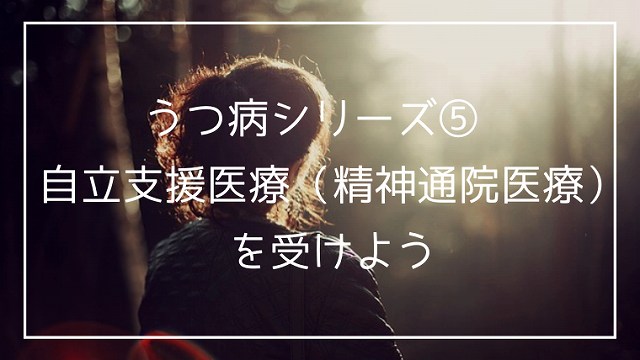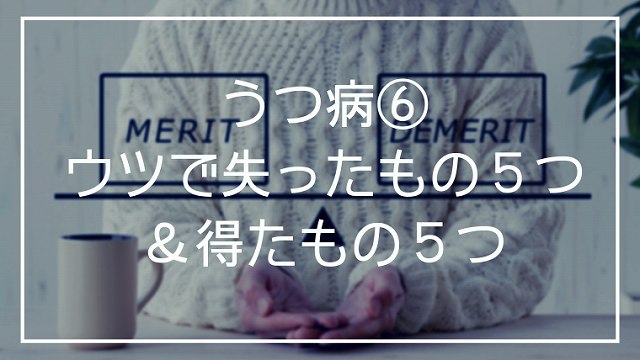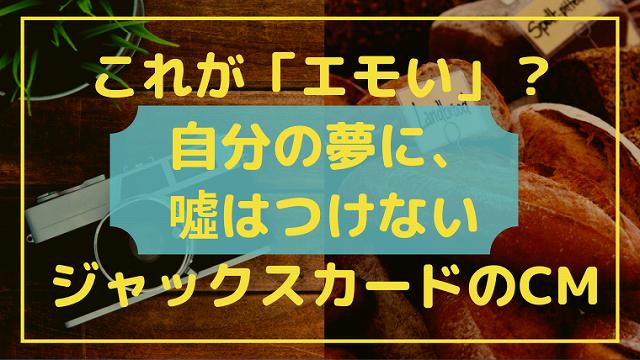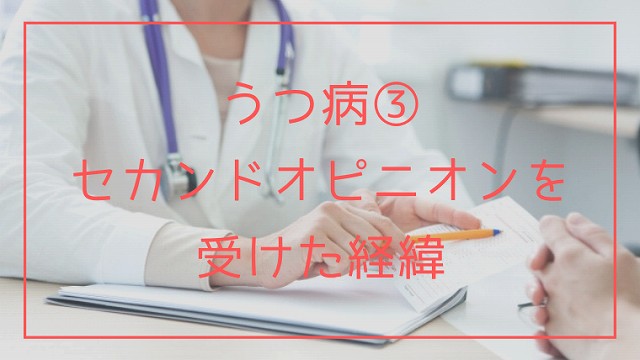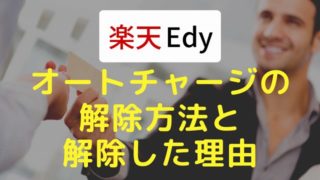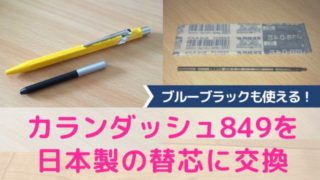こんにちは、ゆとり主婦のマリー(@yutori_shuhu)です。
私はうつ病にかかって以来、気持ちが沈む日が続くと「もしかして、またうつ病では?」と心配するようになりました。
この記事では、私がウツの再発防止のために普段から心がけていることを7つご紹介します。
うつ病ではない人も、予防のために参考にしていただけたら嬉しいです。
最初に結論を言ってしまうと、下の目次の中で「6、気がのらない誘いや付き合いを断る」が私にとって1番効果的で、大事にしていることです。
うつ病の再発を防ぐためにしている7つのこと
改めて、私がうつ病の再発防止のためにしていることを振り返ってみると、習慣的なことから、精神的なことまで、大きく7つあることがわかりました。
1、日光浴 太陽の下で散歩

うつ病の発症の原因は複雑ですが、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れたり、伝達がうまくいかなかったりすることが原因の1つだといわれています。
過剰なストレスや過労などが引き金となって、神経伝達物質のうち、セロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンの量が減少したり、はたらきが低下してくると、さまざまなうつ病の症状があらわれるのではないかといわれています。
出典:うつ病 こころとからだ
その神経伝達物質の中でも、セロトニンは日光を浴びて適度な運動をすることで活性化されます。

そのため、天気がよければ外に出て日光に当たるようにしています。
- 歩いて買い物に行く
- 散歩する
- カフェに行き窓辺で作業する
特に私の場合は、今住んでいる部屋に引っ越して最初の冬にうつ病を発症したため、日光不足には用心しています。
我が家は南西向きの賃貸マンションで、向かい側には高い建物もあり、直接日が射しこむような部屋ではありません。
部屋は日当たりがあまり良くない上に、冬で日照時間がどんどん短くなり、気分がよけいに落ち込んでいったと思います。
「冬季うつ(季節性うつ病)」という言葉があるくらいなので、冬にこそ積極的に日光に当たるように行動しています。
2、鉄分のサプリメントを飲む
私はうつ病になってから様々な関連書籍を読みました。
情報を集めるうちに「食事の内容」が人間の気分や感情に影響を与えることがわかりました。
特にわかりやすかったのが以前にレビュー記事を書いた「食べてうつぬけ」です。
【過去記事】マンガでわかる ココロの不調回復 食べてうつぬけ 奥平 智之著【書評】
(2024/07/27 09:45:17時点 楽天市場調べ-詳細)
本の中では鉄分やミネラルなど栄養素の大切さが書かれています。
特に私は本書が警告する「テケジョ=鉄分不足女子」に該当する懸念があったので、鉄分を摂取できるサプリメントを飲むようになりました。
もともと女性は鉄分が不足しがちなので、メンタルのためだけじゃなく、体のためにもいいと思って続けています。
3、腸内環境の改善のために菌活する(ココカラケアも)
うつ病を発症した当初の勤務先の上司が、私に腸内環境の大切さを教えてくれました。
正直言うとこの時、「何言っているんだろう・・・こっちは大変なんだから納豆で何とかなるわけないじゃない」とまじめに話を聞いていませんでした。
ところが、NHKのドキュメンタリーで「人体 神秘の巨大ネットワーク」という番組を見た際、腸がすばらしい臓器であることや、内臓が脳に影響を与えていることがわかり、考えを改めたのでした。
まず腸内環境を整えるために、菌活を始めました。そして続けています。
菌活1、ヨーグルトの「ビフィックス」を食べる
ヨーグルトは体質に合う、合わないがあると思います。
さらに、ヨーグルトのメーカーや商品に使われている菌の種類によっても便秘が治ったり治らなかったりと、個人差が大きい食べ物です。

私はいろいろなヨーグルトを試した結果、「江崎グリコのBifiX(ビフィックス)ヨーグルト」を食べると、便通が快適になる=体質に合っていて腸の働きが正常に促されているとわかりました。
無糖タイプもあり、スーパーで簡単に手に入ります。
ビフィックスの公式ホームページにある「ビフィックスマガジン」では「腸内フローラ」についてこう書かれています。
「脳腸相関」といって、脳と腸が互いに影響し合っていることもわかってきました。
「緊張するとおなかを下すように、ストレスがあると脳の影響で腸が不調になるのは、以前から指摘されていました。また、IBS(過敏性腸症候群)などで腸がけいれんするような嫌な刺激があると、不快な感覚が自律神経を介して大脳に伝わり、情動をつかさどる大脳の部位に刺激を与え、抑うつや不安といった精神症状にも関係することが明らかになってきたのです」(齊藤さん)
出典:ビフィックスマガジン
脳と腸の関係は、これからも意識して大事にしていきたいです。
菌活2、味噌汁を作って飲む
菌活を始めてからは、伝統的な発酵食品を取るようにしています。
納豆やキムチはもちろんのこと、みそ汁は毎日食べても飽きない万能選手です。

様々な具をたっぷりと入れて、おかずの1つとして飲んで&食べています。
暖かいもの飲み物は、心がホッとできます。
できるだけ1日1回、みそ汁を飲むように心がけています。
参考にしている本は、土井善春さんの「一汁一菜でよいという提案」です。
【過去記事】料理の呪縛から解放してくれる「一汁一菜でよいという提案」土井善晴 著【書評】
(2024/07/27 09:45:17時点 楽天市場調べ-詳細)
みそ汁の常識がくつがえり、具に何でも入れるようになりますよ(笑)
菌活3、「ココカラケア」(ガセリ菌のサプリメント)を飲む
私がうつ病になったと告白した後、母が心配して勧めてくれた乳酸菌のサプリメントです。
アサヒカルピスウェルネス株式会社が販売しています。
 これがココカラケアです。パウチでかさばりません。
これがココカラケアです。パウチでかさばりません。
乳酸菌飲料でおなじみの「カルピス」。
その研究の中から発見された「C-23ガセリ菌」という乳酸菌が配合されています。
「腸とメンタルの関係」を私まだ知らなかった頃だったので、半信半疑で飲み始めました。
まあ、便秘に効けばいいかなくらいの気持ちでした。
実際には便秘にはそれほど効きませんでした。効能にも書いてありませんしね(笑)
あくまでも乳酸菌を含む「食品」なので、抗うつ剤と併用しても問題がなく、飲み続けてきました。
飲んでいる間に転院したこともありますが、良い方向に向かって最終的に9か月で治療を終えることができました。
少しは効果があるのかな~と思って、治療が終わっても飲んでいます。
多少ストレスがかかる嫌なことがあっても、流せるようになってきた気もします。
4、ウォーキングなどのリズム運動
日光浴の項目と少し重複しますが、私は外に出る用事があるときは、なるべく徒歩で行くようにしています。

ウォーキングなど、一定のリズムで運動する「リズム運動」は、うつ病と関わりのある神経伝達物質「セロトニン」を分泌してくれます。
心地よいと感じる強度で有酸素運動を続けることによって、セロトニンなどの神経伝達物質(神経と神経で連絡を取り合う物質)が分泌されるのです。
セロトニンは別名「幸せホルモン」とも呼ばれ、脳の中で感情や記憶を司る部分にセロトニンが伝達すると、精神的な落ち着きが得られると言われています。
リズムよく歩いているだけなのに、前向きな気分になったり、急にいいアイデアが降ってきたりするのは不思議なものです。
5、新しいことを始める前に、いったんブレーキ
私はもともと好奇心が強く、新しいことを次々に始めたくなるタイプです。
しかし、色々と始めるのはいいものの、忙しくなりすぎたり、自分で自分にプレッシャーをかけすぎたりと、生活がハードになる傾向があります。
そのため、何かにチャレンジしたいと思ったときには、一呼吸置くようにしています。
2~3日経つと「なんでやりたかったのかな~?」と熱が冷めていることもあります。
熱が冷めずに「やっぱりやりたい!」と思えた時には許可することにしています。
また、やってみて辛かったら、無理をせずに中断する・止めることも検討します。
とにかく、自分で自分に精神的なストレスを与えないことを意識しています。
6、気がのらない誘いや付き合いを断る
明日、来週、来月などの近い将来に好まない予定が入っていると、それまでの間に何度も想像して気分が落ちてしまいます。
「ああ、来週は飲み会だ」
「明日はいよいよ飲み会だ。めんどくさいなあ」といった風に。
そして予定が過ぎ去るまで、繰り返し脳にストレスを与えてしまうのです。

私はうつ病だと診断されて離職してからは、様々な付き合いを断りました。
その習慣は今でも続いています。
本当に会いたい人、一緒にいたい人とだけの時間を大切にして、少しでもストレスを感じる人とは一緒にいる時間を減らしています。
人間関係は大きな喜びももたらしてくれますが、同時に大きなストレスを与える場合もあります。
うつ病の再発を防ぐためにも、極力ストレスを減らしたいので、心から会いたいと思えない人からの誘いや、苦手な人が出席する飲み会などはお断りしています。
特に、ただ居酒屋に集まってワイワイ飲むだけの飲み会には行かなくなりました。
好きな友人から会おうと誘いがあった時には、夜ではなくて「おいしいランチ、食べに行こうよ」と昼間に誘います。
ランチタイムはお得な価格でおいしいものが食べられますし、日光も浴びられます。
話がはずんだらカフェに移動しておいしいスイーツと紅茶・・・心の癒しです。
付き合いで誘われる講演会や勉強会、イベントも断れるようになりました。
「せっかく誘っていただいたのですが、私はもともとそれに興味がないんです」と言えば相手も案外あっさり「そうだったのね~」と受け入れてくれます。
今フリーで引き受けている仕事は、生活があるので全てを好みで選べるわけではありません。
それでも、自分に向いていない作業や、やりとりにストレスを感じるクライアントはなるべく避けるように意識しています。
一方で、「断る」という行為自体が精神的な負担になるという人もいるかもしれません。
私も最初はそうでした。
そんな時には、お互いを尊重しあうコミュニケーション姿勢「アサーション」が、役立ちました。
アサーションは、「私もOKだし、あなたもOKですよ」というスタンスなので、断ることにネガティブさを感じなくなるのです。
アサーションを知るためにお勧めしたい1冊平木典子さんの「アサーション・トレーニング改訂版」のリンクを貼っておきます。
断れる人になろう!「改訂版アサーション・トレーニング ―さわやかな〈自己表現〉のために」平木 典子著【書評】
7、自分のモニタリング
通院が終わってからは、自分自身の体調やメンタルの変化について観察することを心がけています。
具体的には、手帳に日々のことを書き留めて、そして毎月の振り返りをしています。

紙に落とし込んで、視覚化することで自分を客観的に見ることができます。
予定が詰まりすぎていたら⇒「ちょっと忙しい日が続いているんじゃない?黄信号だよ!」。
1週間、運動した記録がなかったら⇒「そろそろウォーキングした方がいいよね」。
1カ月の振り返りで始めたことがいっぱいあったら⇒「飛ばしすぎじゃない?一回整理しよう!」
こんな感じで自分で自分自身をゆる~くコントロールしています。
ちなみに、毎月の振り返りは下記の4つの項目で書き込んでいます。
- その月の主な出来事(始めたこと・終わったこと・事件など)
- 収穫(よかったこと、うれしかったこと)
- 課題(悪かったこと、改善したいこと)
- 来月はどうしたい(目標や改善案)
まとめ
うつ病の再発を防ぐために続けていることや、始めたことがたくさんあります。
中でも自分の実感で効果が大きい思うものを7つご紹介しました。
1番効果的なのはストレスを減らすことで、自分にとって心地よい人間関係を構築することが心を安定させる大切な要因だと考えています。
もちろん、仕事の都合上、人間関係を選べないという人も多いと思います。
そういった人は、コミュニケーションの方法を学ぶというのも1つの手です。
また、認知行動療法もうつ病に効果があると言われています。
うつ病の予防、再発防止の方法はたくさんあります。
自分の性格やライフスタイルに合わせて、できそうなものから試していきましょう。
体の健康はもとより、心の健康は財産です!