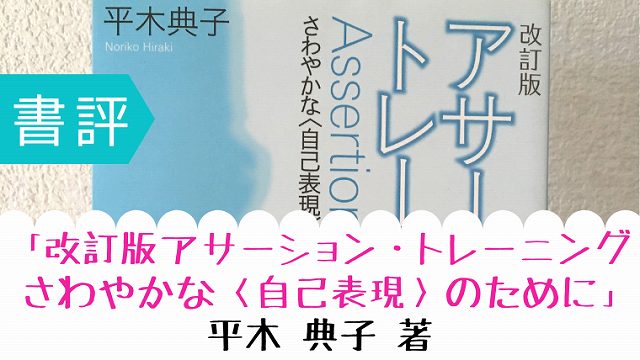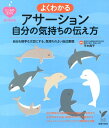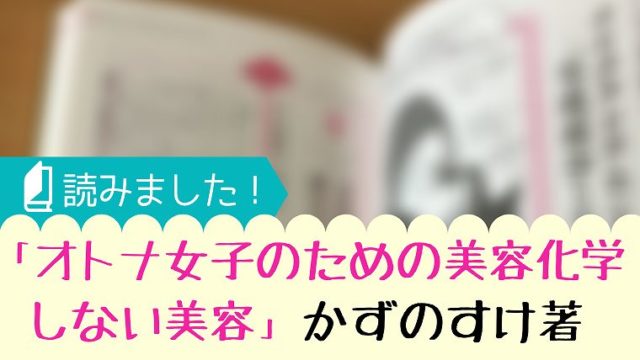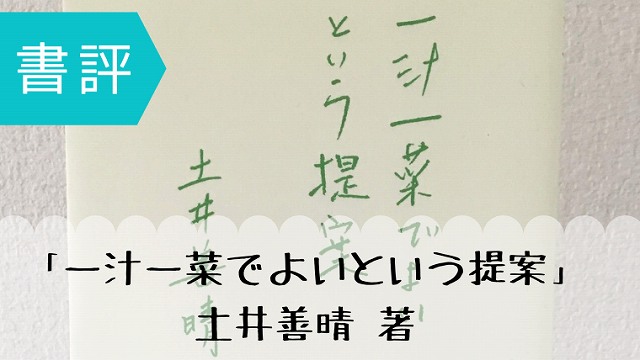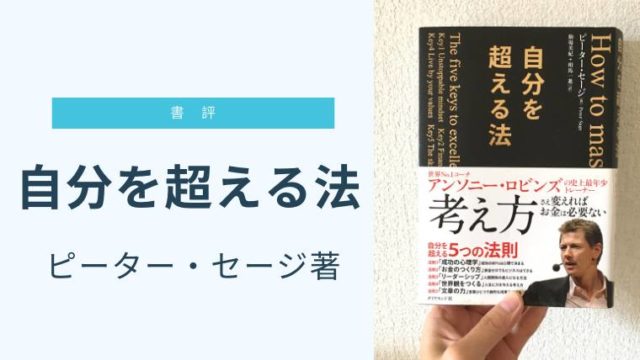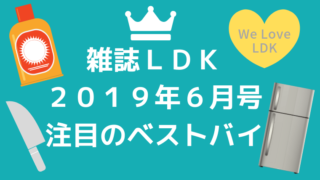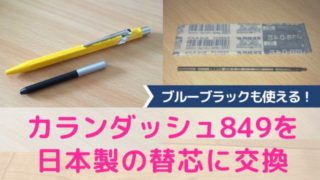こんにちは、ゆとり主婦のマリー(@yutori_shuhu)です。
「アサーション」という言葉を知っていますか?
聞き慣れないし、怪しいカタカナに思われるかもしれませんね。
アサーションとは「自他尊重のコミュニケーション」のことです。
私は、勝間和代さんの著書「断る力」で「アサーティブ」という言葉を初めて知り、そこから関連書籍を読みました。
そこでたどり着いたのが、臨床心理士の平木典子さんが書いた「改訂版アサーショントレーニング―さわやかな〈自己表現〉のために」という本です。
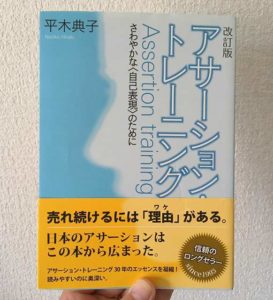
今回は、この本の内容についてレビューします。
私は、アサーションをすべて実践できているわけではありませんが、意識することによって効果を感じています。
例えばこんな、ちょっとしたことができるようになりました。
- あまり興味のない飲み会の誘いを断れる
- 招かれた場で嫌いな食べ物を残せる
- 友達との割り勘がうまくできる
小さなことですが、日々の人間関係の中で、心持ちが少し楽になったような気がします。
もしも下記に1つでも当てはまるなら、あなたにとっても「アサーション」は役立つかもしれません。
- 夜中に友人から電話がかかってきて、眠いのに長電話に付き合ってしまう人
- 家族に「家事を手伝って」とお願いするつもりがケンカになってしまう人
- 予定があるのに残業を断れない人
- 常識にとらわれた思い込みが多い人(~ねばならない)
- 嫌われることが怖い人
- 心理学に興味がある人
こうして並べてみると、ほとんどの日本人に該当するかも!?
何なら、小学校の授業で教えてほしかったと思うくらい、大事なコミュニケーションの根幹が書かれています。
教科書にしてほしいくらいです!
と思ったら、お子さまに教えるための本もありました(^^♪
(2024/07/26 15:04:07時点 楽天市場調べ-詳細)
「改訂版アサーション・トレーニング」の要点3つ
私が本書を読んで大事だと思った箇所の要点を3つご紹介します。
1、アサーションとは何だろう?
まずアサーションとは何なのかという点です。
アサーションはアメリカが発祥で、1970年代に黒人や女性への人権侵害を撤廃する運動ともに広まりました。
日本では、臨床心理士の平木典子さんが1993年に「アサーショントレーニング―さわやかな「自己表現」のために」を出版してから、認知度が高まりました。
アサーションは、「自他尊重のコミュニケーション」や「さわやかな自己表現」を意味します。
わかりやすく具体例をご紹介します。
例)あなたは郷里から上京してきた友人を連れてレストランに行き、ステーキをレアの焼き加減で注文しました。
ところが、ウェイターが持ってきたステーキはウェル・ダンでよく焼けてしまっていました。
その時あなたはどうしますか?
う~ん、これってあるあるですよね?

注文と違うものが来てしまうこともありますし、私の知人には「ラーメンに虫が入っていたのに、お店に悪いと思ってそのまま食べた」という人もいます。
ここでは、3パターンに分けて行動例が挙げられていました。
友人には愚痴を言うけれど、ウェイターには何も言わずに笑顔で対応。
作り直しを要求できなかったことと、友人をこんなレストランに連れてきてしまったことを後悔する。
自分がすっかり委縮してしまった感じになる。
ウェイターを呼びつけて怒る。
必要以上の大声で怒鳴り、もう一皿レアのステーキを要求する。
結果、要求が通ったことととステーキの味には満足できたが、場の雰囲気が悪くなり、友人に対してきまり悪く感じる。
一方でウェイターは侮辱された気がして不愉快になる。
ウェイターに自分の注文と違っていた事実を丁寧に、はっきりと伝える。
また、レアのステーキと交換することを頼む。ウェイターは間違いを謝って交換する。
レアのステーキで友人との食事は楽しくおいしいものになる。自分の行動にも満足できる。
ウェイターも客が気持ちよく過ごせたことで気分がよくなる。
なるほど、最後のアサーティブな人の行動例では、誰もが傷つかずに気持ちよく過ごせそうですね。
「ステーキを作り直したお店が損をしたのでは?」と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、お店側としては客が不満を伝えずに2度と来なくなる方が損失です。
本書には書かれていませんが、日本人の顧客は不満があると黙って店を去ることから「サイレントクレーマー」と呼ばれることがあります。
間違いを伝えてもらって、作り直して満足してもらい、リピーターになってもらえた方がお店側にはメリットが大きいですよね。

もちろん、これ以外の選択肢もあると思います。
私が考える別の例としては、「ウェル・ダンもたまには食べてみようかな?」と友人に相談して、2人とも納得の上でウェイターに交換を頼まずに食べてみる。
それとプラスアルファで伝えたければ、ウェイターに「注文とは違うようだけど、ウェル・ダンも食べてみたいからこのままでいいよ」と伝える。
などが考えられます。
いずれにせよ、自分が不満を抱えたままにしていない、相手や周囲を傷つけずに、納得できる行動をとることがアサーティブ的なふるまいなのだと私は理解しました。
2、考え方をアサーティブにしよう
アサーティブな言動には、自分が普段から考えていることや価値観、ものの見方などが影響します。
非合理的な思い込みがあると、問題や悩みが作られやすくなります。
例えば、「人は誰からも愛されて、常に受け入れられるようにしなければならない」という思い込みはどうでしょうか?
100人の知り合いがいて、その100人全てから愛されるなんて、難しい話ですよね?

しかし、冷静に考えれば非合理だとわかっても、すりこまれてしまった思い込みは根強くあります。
その結果、この例で言えば人に嫌われないようにするために、自分の意見や希望は極力言わず、逆らわず、もめごとを避けるようになります。
いわゆる「いい子」や「イエスマン」になるかもしれません。
相手に気に入られるような行動を取る=アサーティブな振る舞いができなる。
結果として、自分らしさを確立しにくくなります。
非合理な思い込みを合理的なものにするには「人に好かれることに越したことはなけれど、必ず好かれるとは限らないし、好かれなければならないこともない」という考えに変えることです。
考え方を変えることで、自分自身が楽になり、アサーティブな態度が取れるようになります。
3、アサーティブな表現とは
では、実際にはどういう表現をすればアサーティブだと言えるのでしょうか。
アサーションには、言語的なものと、非言語的なものに分けられます。
さらに言語的なものをわかりやすく分けると、2つになります。
- 日常会話の場=メンテナンスのアサーション
- 議論や課題達成・問題解決の場=タスクのアサーション
そのうち、「タスクのアサーション」の方が、私は苦手意識があって難しく感じています。
課題達成・問題解決(タスク)のためのアサーションとは、会議の場、話し合いで何かを決めたり課題を達成したりする場におけるアサーションのことです。
あるいは、うまく言えそうもないことを言おうとするとき、何と言ったらいいか迷う時、話が複雑できちんと整理する必要があるとき、自分の気持ちや考えを明確にしてから話す必要があるとき、などに役立つ言い方のことです。
P117 第4章アサーティブな表現より
このタスクのアサーションを成功させるためには、「DESC法」が有効だと書かれています。
「DESC法」の概要をご紹介します。
D・・・describe・描写する
E・・・express・表現する、explain・説明する、empathize・共感する
S・・・specify・特定の提案をする
C・・・choose・選択する(選択肢を提案する)
いずれの項目も、感情的にならず明確に、客観的に述べることが大切です。
わかりやすい例が挙げられていました。
あなたはカフェで喫煙席の近くの禁煙席で友人と話をしています。友人は煙草を吸うけれど、自分は吸わないため、好ましくない状況です。
この場合、どんなふうにタスクのアサーションを行ったらよいでしょうか?
下記は、DESC法を使ったアサーティブな表現の例です。
ここは喫煙席に近いので、煙が流れてきますね(D)。
私は煙草の煙が苦手で、のどが痛くなってきました(E)。
あなたは煙草が吸いたくなっているかもしれませんね(E)。
そろそろここを出ませんか(S)。
そうすればあなたは煙草の誘惑から逃れられますし、私は助かります(肯定的結果に対するC)。
もし、あなたが一服したいのでしたら、あちらの席に行って一服してから、喫煙席から離れたところに移りませんか(提案が受け入れられなかった場合のC)。
P118 第4章アサーティブな表現より
実際には会話ですから、この通りに一人でしゃべり続けるわけではないでしょう。
ただ、とても参考になるのは、事実を述べているだけで誰かを責めるようなことを言っていないので自分も相手も傷つかないことです。
また、選択肢を複数提案することで、相手を尊重する姿勢を表現できています。
もし、アサーションを意識せずに席を移りたいと思ったら、私だったらこう言うかもしれません。
「この席さ、煙流れてくるね。なんでここに座っちゃったんだろう~。ここから遠い席に移らない?あ、でも○○さん(相手)は煙草吸うんだっけ・・・」
結果として、相手は責められたように感じたり、私は自分自身の身勝手で申し訳ない気持ちになったりするかもしれません。
相手が煙草を吸う人であることを尊重しつつ、自分の希望を伝えられるのがタスクのアサーションの優れた点なのです。
感動ポイント!「基本的アサーション権」で涙が・・・
アサーションに関する権利は100以上あると言われるそうです。
中でも本書の中で取り上げられている5つの基本的な権利を取り上げます。
私は読むだけで涙がほろりと出そうになります。
当たり前のことが当たり前でない社会で私たちは生きている。
もしくは、私たちはとても不器用な生き物なのだと実感するような内容です。
1、私たちは、誰からも尊重され、大切にしてもらう権利がある。
これ、当たり前のようでいて、自分のこととなると当たり前ではなくなるんですよね。
誰かから傷つけられ不当な扱いを受けた時、相手のことを責めるよりも「自分には価値がないから、仕方がない」とあきらめてしまうこと、ありませんか?
人間がそれぞれ、気持ちや価値観を尊重してもらう権利があるということは、自分自身にもその権利があるということ。
自分に権利を認めずに我慢していませんか?
「嫌です」「私はこれがしたいです」など、気持ちや欲求を伝えていいのです。
私たちには一人一人にその権利があるのです。
自分の権利を自分で守ってあげましょう。
2、私たちは誰もが、他人の期待に応えるかどうかなど、自分の行動を決め、それを表現し、その結果について責任をもつ権利がある。
この権利は奥が深いです。後半の「責任をもつ権利がある」に注目してください。
ここで意味する「責任」とは、自分の決断に対する責任です。
例えば、あなたが伴侶から「今度の週末、実家に帰省しよう」と言われたとします。

しかしあなたは週末にまとまった時間を取ってブログを書こうと思っていました。
一度断っても伴侶が「母さんがたまにはおまえの顔も見たいってさ」とあきらめません。
さて、どんな選択をして、伴侶にはどう伝えましょう・・・?
ここでは、「行く」「行かない」どちらの決断が正解ということはありません。
どちらも選ぶにしても、それを決めるのは自分自身であり、最終権限は自分にあり、その結果に対して責任を取るのも自分である、という権利なのです。
もし「行く」決断をして行ったのなら、いつまでも「めんどうだなあ。アイツはお義母さんの機嫌ばかりとって・・・」など誰かを責めていても仕方ないのです。
決めたのは自分なので、行くことに対する責任はあなたにあります。伴侶にも義母にもないのです。
一方で、「行かない」決断をしたのなら、「あ~、伴侶を怒らせちゃったかな。お義母さんもガッカリしているかも」などと、ウジウジ考えている必要はないのです。
あなたが「行かない」と決めて表現して行動した結果の責任は、あなたにあります。
その覚悟をしましょう。
それで起こることに対しては、できる範囲で責任を取ればいいというわけです。
3、私たちは誰でも過ちをし、それに責任をもつ権利がある。
失敗しない人間はいません。
もしも失敗が許されない社会だったら、何も身動きがとれません。
また、失敗する人間はダメだという考えは、自己卑下につながり、自信が失われます。
自分が過ちを犯してしまった時、隠さずに誠意をもって謝り、できる限りの償いをすることは、権利なのです。
これが上手くできないと、自分が失敗をした時に、他の人からミスを指摘されたり責められたりすると、逆ギレしてしまいがちです。つまり、アサーティブではなく攻撃的なコミュニケーションですね。
結果として、過ちに責任をもつ権利を使い損なってしまいます。
4、私たちには、支払いに見合ったものを得る権利がある。
「支払いに見合ったものを得る権利」も当然のようですが、自分自身に認めていますか?

私は20代の頃、洋服を買って、自宅に帰って広げてから、服の脇の部分の糸がほつれて穴になっているのを見つけてことがあります。
でも、タグを切り取ってしまった後だったし、クレーマーだと思われなくない気持ちもあり、それを交換して欲しいとお店に伝えることはできず、自分で慣れない補修をしました。
もし、「服の代金を払った分の価値を手に入れる権利が私にはある」と信じていたら、迷わずに「交換してもらう」選択をしていたでしょう。
ただし、次の項目にも書きますが、「交換して」と言うことや店に持参することが面倒だから、あえて主張しないことを「私が選ぶ」という権利もあります。
5、私たちには自己主張をしない権利もある。
これまで見てきたように、アサーションを勉強すると、ついつい「使わなくては」と思い込んでどんな場面でも使おうとするかもしれません。
しかし、時間的なロスを考慮した上でアサーションと釣り合わないと思った時や、アサーションすると身の危険を感じる時は、「アサーションしない権利」を使うことができます。
例えばラーメン屋さんの行列にに並んでいる時、ちょっと怖そうな(その道の)人が横入りしてきたとします。
私だったら、そこは、やはりスルーして「アサーションしない権利」を使いますね・・・
何がなんでもアサーションを使おうとして、生活に困難が生じたら元も子もありません。
まとめ・感想 まずはアサーションを知ろう!
私は、自分がアサーションを実践できるようになれば、もっと生きやすくなるなと思いました。
特に、10代、20代の頃の「断れなかった」「自分の意見を言うことに罪悪感を感じていた」自分に教えてあげたい内容です。
「誘いを断ったり、違う意見を言うと、相手を傷つけるのではないか」という不合理な思い込みを私から追い払ってくれた本です。
また、多くの日本人にとっても、アサーションの知識とスキルを得られれば、
少なくとも考え方を知っているだけでも、生きるのが楽になるだろうと思います。
まずはこの1冊でアサーションを知りましょう!
文字だけだと読みにくい方には、こちらも平木典子先生のアサーション本ですが、イラストと図解があるため、併せておすすめします!
レビュー評価も高い1冊です。
また、お子さまと一緒に学んでいきたい方にはワークブックもあります。
(2024/07/26 15:04:07時点 楽天市場調べ-詳細)